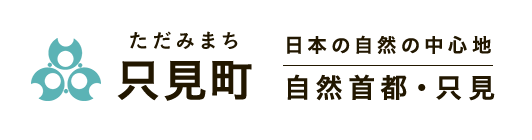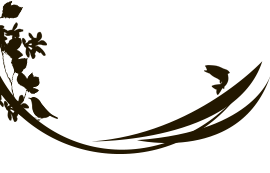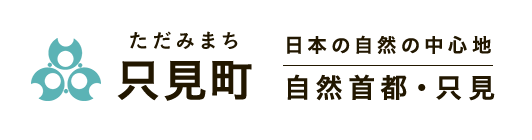入院時食事療養費及び生活療養費の標準負担額の見直し
入院と在宅療養の負担の公平を図る観点から、平成28年4月1日から1食につき360円、平成30年4月1日から1食につき460円に見直されることとなりました。ただし、低所得者の負担額は引上げないこととするほか、指定難病又は小児慢性特定疾病若しくは平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院していた一般所得区分の患者の負担額については、現行の1食につき260円を、当分の間据え置くこととなりました。
- 入院時の標準負担額(一般病床・精神病床等、療養病床(65歳未満又は医療区分Ⅱ・Ⅲ))
| 区分 | 食費(1食当たり) |
|---|
| ~H28.3 | H28.4~ | H30.4~ |
|---|
| 一般(下記以外の人) |
260円 |
360円 |
460円 |
住民税非課税世帯
(70歳以上の人は低所得Ⅱ※2) |
過去12ヶ月で90日までの入院 |
210円 |
| 過去12ヶ月で90日を越える入院 |
160円 |
| 低所得Ⅰ※3 |
100円 |
- 65歳以上の人が療養病床(医療区分Ⅰ)に入院したときの標準負担額
| 区分 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) |
|---|
| 一般(下記以外の人) |
460円 |
320円 |
住民税非課税世帯
(70歳以上の人は低所得Ⅱ) |
210円 |
| 低所得Ⅰ |
130円 |
- ※2 低所得Ⅱとは、世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人。
- ※3 低所得Ⅰとは、世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費等を控除したときに0円となる人。
- 住民税非課税世帯の方が入院されるときは、あらかじめ標準負担額減額認定申請(郵送可)をしてください。また、入院日数が90日を超えるときには再度交付申請をしてください。(平成6年9月9日保険発第114号厚生省保険局国民健康保険課長通知)
- 標準負担額減額認定証は、申請のあった日の属する月の初日から使用できます。
- 入院日数が90日を超えたときは、申請のあった日の属する月の翌月の初日から使用できます。また、標準負担額減額差額支給申請をすることにより、申請のあった日の属する月の末日までの標準負担額の差額が支給されます。
- 医療区分
| 医療区分Ⅲ |
- 疾患・状態
- スモン
- 医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態
- 医療処置
- 24時間持続点滴
- 中心静脈栄養
- 人工呼吸器使用
- ドレーン法
- 胸腹腔洗浄
- 発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管
- 感染隔離室における管理
- 酸素療法(酸素を必要とする状態かを毎月確認)
|
|---|
| 医療区分Ⅱ |
- 疾患・状態
- 筋ジストロフィー
- 多発性硬化症
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病関連疾患
- その他の難病(スモンを除く)
- 脊髄損傷(頸髄損傷)
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍
- 肺炎
- 尿路感染症
- リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内
- 脱水かつ発熱を伴う状態
- 体内出血
- 頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態
- 褥瘡
- 末梢循環障害による下肢末端開放創
- せん妄
- うつ状態
- 暴行が毎日みられる状態(原因・治療方針を医師を含め検討)
- 医療処置
- 透析
- 発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養
- 喀痰吸引(1日8回以上)
- 気管切開・気管内挿管のケア
- 頻回の血糖検査
- 創傷(皮膚潰瘍・手術創・創傷処置)
|
|---|
| 医療区分Ⅰ |
医療区分Ⅱ・Ⅲに該当しない人 |
|---|
課税限度額の見直し及び低所得者に係る保険税軽減の拡充
被保険者間の保険税負担の公平の確保及び中低所得層の保険税負担の軽減を図るため、平成27年度に引続き平成28年度から、医療給付費分及び後期高齢者支援金分の課税限度額が見直されることとなりました。また、低所得者の保険税を軽減するため、応益保険税(均等割、平等割)の5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の基準が見直されることとなりました。
- 国保税の医療給付費分の課税限度額が54万円(現行:52万円)に、後期高齢者支援金分の課税限度額が19万円(現行:17万円)に引き上げます。
- 医療給付費分・後期高齢者支援金分の課税限度額は73万円(現行:69万円)になります。
- 介護納付金分の課税限度額は16万円のままです。
- 国保税の軽減措置について、軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額が5割軽減の対象となる世帯では26万5千円(現行:26万円)に、2割軽減の対象となる世帯では48万円(現行:47万円)に引き上げます。
- ① 総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円を超えない世帯は、均等割、平等割が7割軽減されます。
- ② 総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき26万5千円を加算した金額を超えない世帯は、均等割、平等割が5割軽減されます。
- ③ 総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき48万円を加算した金額を超えない世帯は、均等割、平等割が2割軽減されます。